こんにちは、GROOVE Xのスクラムマスターの1人、niwanoです。GROOVE X Advent Calendar 2024の12日目の記事です。 今日は、評価制度を作っている話をお届けします。
庭師と領域人事
人事チームとスクラムマスターチームが「組織のお手入れをする」という名目で活動するワーキンググループがあります。このグループは "庭師" と呼ばれています。
2024年から、スクラムマスターは領域人事という役割を担うようになりました。開発領域における一部の人事業務をスクラムマスターがカバーする形です。その活動の一例が、今回の評価制度の作成です。
評価制度はなぜ必要か
スタートアップでは評価制度が整っていないことも少なくありませんが、弊社もこれまで360度評価を散発的に実施していたものの、人事評価には直接反映してはいませんでした。
みなさんは、評価制度がなぜ必要だと思いますか?
- 自分のお給料のため?
- 公平性のため?
どちらも正しいですが、庭師では、評価制度を社員の成長のために必要なものと考えています。 まず社員の成長があり、それが会社の成長につながり、結果としてお給料の原資が確保される、という仕組みです。 そのため、評価制度は社員の苦手な項目を明確にし、成長目標の指針となるものでなければなりません。
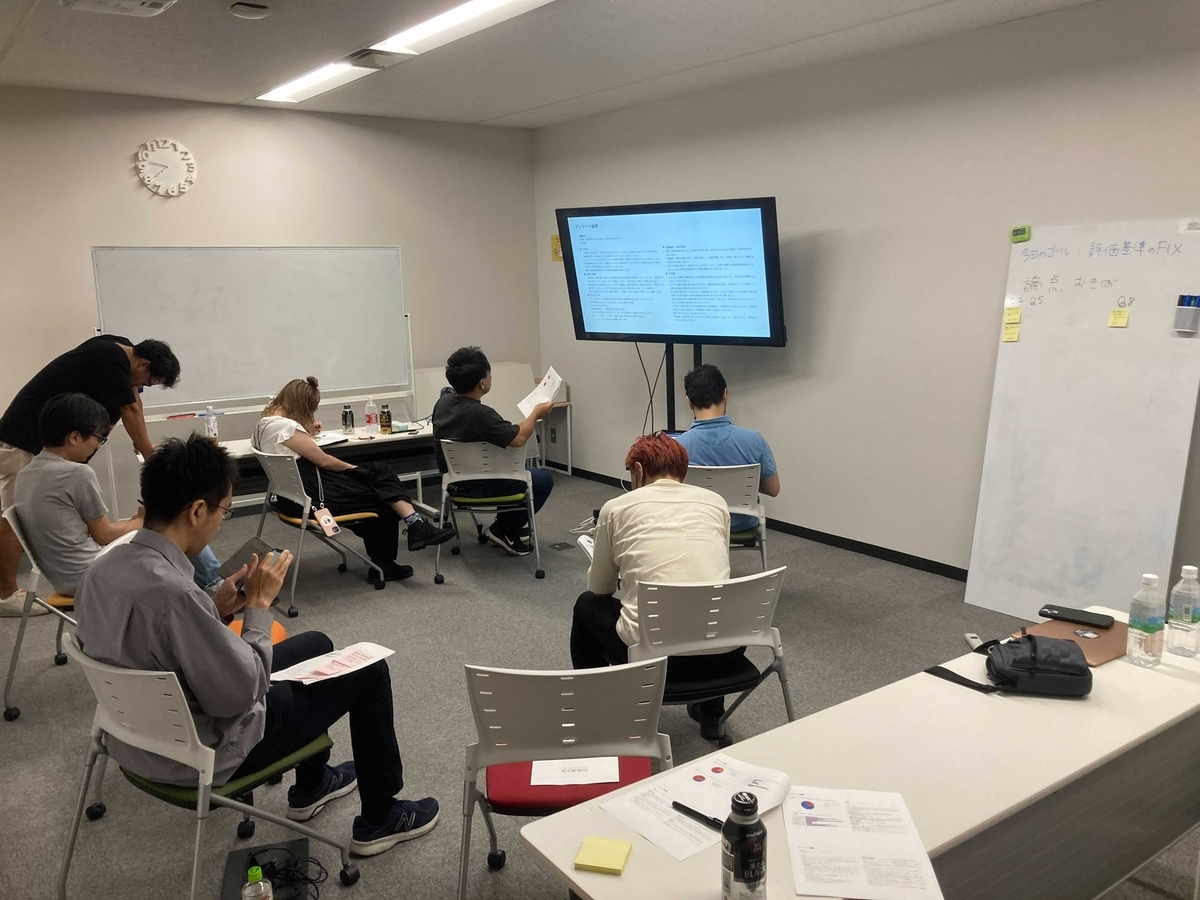
みんなでつくる評価制度
CEOによって評価制度のたたき台が作成された後、全社員でのレビュー会が行われました。 これは非常に弊社らしい試みだと感じました。 社員が評価制度の作成に参加できる機会は滅多にありません。 この丁寧なレビュー会を通じて、社員が制度に納得し、その内容を深く理解できるだけでなく、人に説明できるようになります。
評価項目の一例
ここで、私のお気に入りの評価項目を2つ紹介します。 (評価項目は全部で17項目あり、すべて紹介すると今年のアドベントカレンダーが埋まってしまいます!)
リーダーシップ
背景説明
リーダーシップとは、自らが組織やチームの一員であると自覚し、「自分ごと」として捉える姿勢です。 自分だけでなく周囲を巻き込み、目標達成に向けて積極的に推進することで、全体の成果を最大化します。 これは「自分の境界」をどこに持つのか、とも言い換えられます。 自分の境界を自分の皮膚に持つのか、チームに持つのか、事業に持つのか、お客様を含めた全ステークスホルダーに持つのか。 それによって守ろうとする対象が変わります。これが広い方が、「自分の境界」が広いと言えます。 リーダーシップは、他者の協力を引き出すコミュニケーションと信頼関係の構築によって強化され、周囲にポジティブな影響を与えます。
「境界を自分の皮膚にもつ」という表現は非常に的確で、私のお気に入りです。 自分の境界を拡げていきたいですよね!
コーチャビリティ
背景説明
コーチャビリティとは、他者からのフィードバックを前向きに受け入れ、自己改善や成長につなげる能力のことです。 特にギャップフィードバックを受けた際、言い訳したり、黙り込んだり、相手を攻撃したくなるのは自然な自己防衛反応です。 しかし「良薬口に苦し」と言われるように、冷静に受け止め、そこから学ぶ姿勢を持つことで成長が可能になります。 相手の意図を理解し、自分にとって有益なポイントを見つけ出すことで、より高いパフォーマンスを実現できます。 この姿勢は周囲との信頼関係を強化し、チーム全体の成長にも寄与します。 現代のビジネス環境では変化が激しく、継続的な学習と適応が求められます。 フィードバックを適切に受け止めることは、自身の成長だけでなく、組織全体の成果向上にもつながります。
ギャップフィードバックこそが社員の成長につながると考えています。 それを受け入れる能力、つまりコーチャビリティが重要です。 ギャップフィードバックをする側も高いストレスを感じる作業であることを、忘れてはいけません。
(ギャップフィードバックはネガティブなフィードバックのこと)
17項目の評価制度をどのように成長につなげるか
庭師では、自己評価と他者評価を比較し、ギャップが明確になるような仕組みを考えています。
| 自己評価 | 他者評価 | アクション |
|---|---|---|
| 低い | 低い | 要改善 |
| 高い | 低い | 最重要で改善 |
| 低い | 高い | コーチャブルになる。自己評価の基準を見直す。 |
| 高い | 高い | さらに磨く。周囲にその能力を還元する。 |
このようにギャップを明示することで、成長目標を設定しやすくなります。
満点をとらなくてもいい
評価項目が設定されると、すべてを満点にしたくなるものですが、庭師ではその必要はないと考えています。 指標は以下の4段階です。
- Mentor: GROOVE Xの模範
- Very good: 十分な成果を出している
- Nice Try: 頑張っている
- Early stages: 伸びしろたっぷり
たとえば、リーダーシップの、Very Good と Mentor は、以下のようになっており、とても高いレベルのものになっています。
Very good
自分の仕事の範囲を自チームと関係する周辺のステークホルダーの広い幅では捉えているので、関係するチームのメンバーとしてやりやすい。
Mentor
very goodにプラスして、以下が達成されている。 ・お客様や事業のためであれば解決すべき課題をよく考えていて、問題を発見する能力に長けている。 ・発見した問題に対して、(自チームやステークスホルダーにとって辛いことでも見て見ぬふりをせず、)周囲を巻き込んで解決するために行動ができる。 ・視座が高く、経営目線をもっていると感じる。
まずは「オール Nice Try」を目指すのでも十分です。
最後に
作成中の評価制度は、仕事に対する立ち振る舞いを評価するものです。庭師ではこの評価に加え、スキル評価を取り入れ2軸で社員を評価することを計画中です!
成長し続けることの重要性
これは私の考えです。 私たちは、成長できていない状態、例えば昨年と同じことを繰り返しているような状況では、いつまでも「交換可能な人材」であると考えています。 人は勤務年数が長くなると、その立場に安住してしまいがちですが、絶え間なく成長を続けることで、初めて「交換不可能な人材」になれるのだと思っています。
そして、弊社で最も成長しているのは、他ならぬCEOではないかと感じています。
あれだけ忙しいのに、この評価制度も考えているんです。すごすぎる!
負けませんよ、CEO!
一緒に働く仲間を募集中!
いかがでしたでしょうか? 今回は、現在整備中の評価制度をご紹介しました。 他の評価項目については、また別の機会にお話しできればと思います。
弊社では仲間を募集中です。 ぜひご応募ください!